- HOME >
- 戸建て住宅および店舗などの工法について >
- 地盤調査とは
地盤調査とは、土地を地質学的と土質工学的に調べる事を言います。
地質学とは、土地の地盤の層が、今までどの様に蓄積されて来たかを、調べます。
土質工学とは、土地を物理的と力学的に現状地盤が、どの様な状態か調べます。
地盤調査の主目的は、地盤が構造物を安全に支持できるかどうか、また、安全に支持するための方法を技術的に調べることです。
地盤を構成する土の性質は、他の建築材料である鉄鋼・コンクリート・石材・木材・などと根本的に異なります。特に、土は含まれる水分の量によって、土の性質が変化します。また、土は場所によって堆積過程が異なり、土の粒子の混ざり具合及び締まり具合などが異なるため、他の建築材料のように均一な特性は得られません。
このような土の性質から、構造物の築造や宅地の造成などの工事を行う場合には、その場所毎に地盤の性質を調査・確認する必要があります。
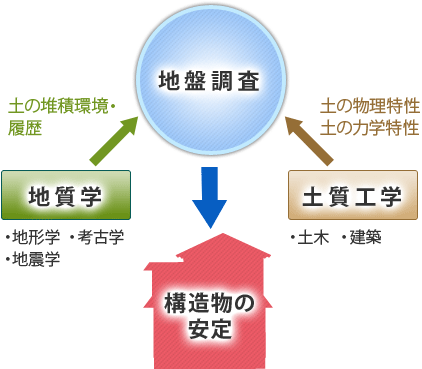
土はいろんな大きさ、形をもった集まりであり、土粒子の間隙には水・空気が含まれています。
土粒子を粒径によって分類すると次のようになります。
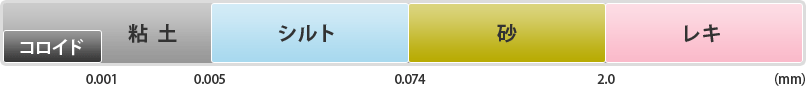
地盤が軟弱地盤か安定地盤かと、いう事は土粒子の間隙の水(含水比)と空気(空隙)の割合で決まります。
水と空気が多い程、軟弱度が増し、逆に少なくなる程、堅い地盤になります。
人々の生活の場である住居、生産活動の拠点としての工場など、その種類・目的・規模の差異を問わず共通しているのは、それらの構造物がすべて地盤の上に建設されている事です。
この様な各種の構造物を安全で機能的かつ経済的に建設する為に、設計・施工に先だって必要な地盤情報を得る事が地盤調査の大きな目的の1つです。
すなわち、地盤が構造物や施設を安全に支持出来るかどうか、また出来ない場合には安全に支持するための方法を技術的に調べる事が調査の要点となります。
地盤の条件と構造物の規模によっては、それ自身の重みなどによって地盤が変状する事が多発しています。
不同沈下以外にも、我が国では集中豪雨・台風・地震などに起因する斜面崩壊や液状化などの地盤災害が多発しています。
災害の防止とその規模の軽減に向けて十分な対策を講じるためにも地盤調査の果たす役割は極めて大きな事です。
建物を支えているのは基礎です。その基礎を支えているのは、さらにその下の地盤です。基礎と地盤の接地面では建物の荷重と地盤の強さが力くらべをしているようなものですが、仮に地盤が軟弱で、建物の荷重に耐えきれないときには、建物は沈下してしまいます。
計画建物の重さに地盤が耐えられるかどうか、見ただけでは分からない地盤の強さが、地盤調査を実施する事によって数値として把握できます。
すなわち、地盤調査の結果を参照する事で、地盤の強さに見合った基礎の仕様を決定できるのです。
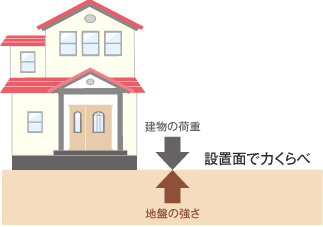
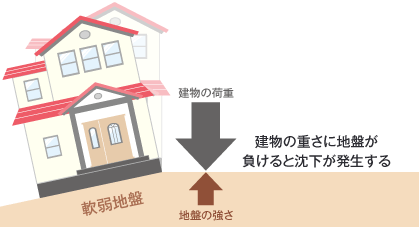
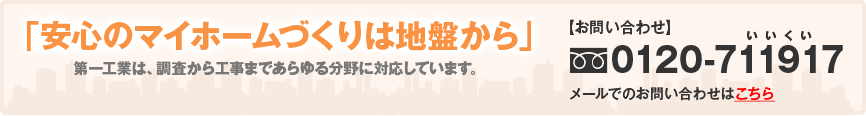
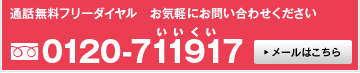

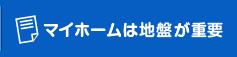
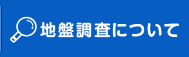

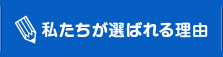
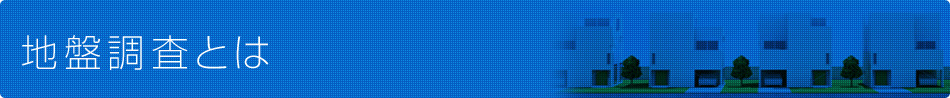
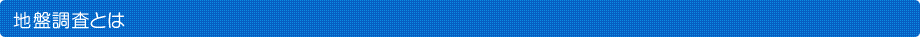


地盤調査・地盤改良・杭・設計・施工・杭打ち・杭抜き・沈下修正の事なら第一工業にお任せください。